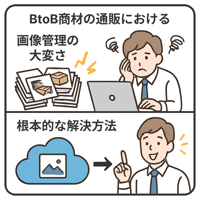...
ヒューマンエラー対策の新戦略:AIによるレジリエンス構築
商品情報の記入やECサイトへの掲載など日々の業務では、転記ミスなどの人的作業によるケアレスミスはつきものです。
そんな「ヒューマンエラー」の研究第一人者である立教大学名誉教授・芳賀繁氏の理論に基づいて、
ヒューマンエラーの発生理由を構造的に解明いたします。
また、こうしたエラーを可能な限り削減するための対策についても併せて解説いたします。
序章:ヒューマンエラーの再定義—なぜ従来の対策は機能しないのか
[ヒューマンエラーの本質的定義]
一般的に「ヒューマンエラー」は個人の不注意や過失として片付けられがちですが、
芳賀繁氏らの提唱する現代的なエラー研究では、その本質が異なると捉えられています。
ヒューマンエラーとは、「安全性、効率性、システムの機能などを損なう人間の決定や行動」であり、
これには「うっかりミス(ポカミス)」だけでなく、意図的な「違反行動」も含まれます。
重要なのは、エラーは個人の能力の問題ではなく、機械システムと人間との関わり、
そして組織全体に潜むシステム的な要因によって起こる現象だという視点です 。
システムが複雑化し、人間が制御するエネルギーの量が増大した現代において、
小さな誤操作や誤った判断が、以前の時代には考えられなかったような大きな被害をもたらすリスクが増大しています。
[従来の対策の限界と行き詰まり]
多くの組織で長年行われてきた「注意喚起」「安全意識の高揚」「基本動作の励行」といった精神論に頼ったエラー対策は、
その効果が限定的であることが指摘されています。
さらに、「失敗ゼロ」を目指してマニュアルや手順を厳しくするほど、現場の作業はがんじがらめになり、
想定外の事態への柔軟な対応が阻害されます。
また、統計的に見ても、人間は完全に正常な状態であってもミスをする可能性はゼロにならず、
ヒューマンエラーを「ゼロ」にすることは不可能であるという現実を認識することが、抜本的な対策の出発点となります。
第1章:ヒューマンエラーが発生する構造的理由
ヒューマンエラーは、個人の心理的・生理的要因だけでなく、組織やシステムに潜む構造的な要因が複合的に作用して発生します。
芳賀氏の「システムズアプローチ」では、エラーは「失敗の原因ではなく、より深いところにある問題の結果として起きる」と見なされます。
[エラーの類型と個人の心理的要因]
ヒューマンエラーは、意図せず発生する「ポカミス」と、意図的な「ルール違反」に分類されます。
|
エラー類型 |
具体的な原因例 |
組織的対策の視点 |
|
記憶エラー |
作業手順やイレギュラーな指示の覚え間違い、マニュアルの記憶の曖昧さ |
マニュアルの明確化と反復学習の仕組み化 |
|
認知エラー |
作業指示書の数字や、形状が似ている部材の見間違い |
ダブルチェック体制の確立、チェックリストによる確認項目の明確化 |
|
判断エラー |
単純作業による集中力低下や、不慣れな状況による誤った判断 |
休息時間の確保、業務量の平準化 |
|
違反行動 |
忙しさによる確認の省略、面倒な手順を自己流に変更 |
ルール変更の提案を促す風土、遵守せざるを得ない仕組みの導入 |
疲労、睡眠不足、加齢といった生理的要因 や、作業への「慣れ」や「慢心」による油断 も、個人の注意力を低下させ、ミスを引き起こす大きな要因です。
[人間の脳に備わる機能]
ここで、人間の脳に備わる高度な機能を知るべく、以下の文章を読んでみてください。

いかがでしょうか。意味を理解することはできたでしょうか。
多くの方はご理解いただけたのではないでしょうか。以下が正しい文章になります。
.jpg?width=960&height=540&name=%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E8%84%B3%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD%20(1).jpg)
これは、タイポグリセミアといって文章中のいくつかの単語で最初と最後の文字以外の順番が入れ替わっても正しく読めてしまう現象です。
この現象は、狭義には2003年9月にインターネット上に出回った都市伝説/インターネット・ミームであり、
ケンブリッジ大学でこのような研究が行われたことはないそうですが、人間の認知に関わる現象として興味深いです。
もしこれが13桁のJANコードの転記作業だとしたら、どうでしょう。
少しゾッとします。
いつも得意先から送られてくる品番と異なる品番でオーダーが入ったとしても、
流れ作業の中で気づかずに処理し、誤配送してしまうかもしれません。
[組織・システムに潜む誘発要因]
個人の特性を超えて、エラーを誘発する組織的・環境的な要因は以下の通りです。
- 単純・反復作業の多さ:
単調な定型業務は集中力の低下や慣れを引き起こし、見落としや思い込みによるヒューマンエラーを招きやすい。 - マニュアル・手順の不備:
作業手順や操作方法が曖昧であること、生産設備が刷新されてもマニュアルが更新されていないこと。曖昧な表現は読み手の解釈のバラつきを生み、作業のバラつきを招きます。 - 作業環境の不整備:
照明不足、騒音による指示の聞き間違い、高温多湿な環境など、作業者の集中力を維持させることが困難な環境。 - コミュニケーション不足:
部署間連携や引き継ぎ時の情報共有のミス、質問や相談がしにくい職場風土。
第2章:対策のパラダイムシフト—レジリエンス・エンジニアリング
従来の安全管理が行き詰まりを迎える中、芳賀氏が提唱するのは、
安全管理の新しい思想である「レジリエンス・エンジニアリング」です。
これは、「失敗ゼロ」を目指す(Safety-I)のではなく、
「安全とは、うまくいくことが可能な限り多い状態」と再定義する考え方(Safety-II)に基づいています。
|
観点 |
従来のSafety-I(失敗を減らす) |
新しいSafety-II(成功を増やす) |
|
目的 |
事故・失敗の発生を防止する |
成功・安全な状態を維持し、強化する |
|
失敗への捉え方 |
失敗は異常な出来事であり、罰せられるべき |
失敗は学習の機会であり、システムの変動で起こる |
|
対策の転換 |
マニュアル強化、罰則、精神論 |
成功要因の強化、柔軟な対応力の向上 |
レジリエンスの考え方に基づき、組織は「ミスをしない人間を訓練する」ことから、
「人間が間違えにくい仕組み・やり方にする」ことに焦点を移す必要があります。
第3章:抜本的な対策:デジタル技術による仕組みの変革
ヒューマンエラーが起こりやすい単純作業や、曖昧な情報伝達の領域こそ、
デジタル技術やシステムの力を活用し、人間が間違えにくい環境を構造的に構築すべきです。
[エラーを誘発する単純作業のシステム的排除]
集中力の低下や慣れによるミスを誘発しやすい単純作業や反復的なデータ転記は、人間よりもシステムが優れています。これらの業務を自動化することで、ヒューマンエラーが発生する機会そのものをシステム的に排除します。
- 定型業務の自動化: データ入力や情報整理といったルーチンワークを自動化することで、従業員は反復的で付加価値の低い業務から解放され、同時に人的ミスによるリスクを最小化します。
- ポカヨケ(フールプルーフ)の導入: 人が誤った操作をしても事故やエラーに繋がらない仕組み(例:規格外品でアラートが鳴る装置、二つのボタンを押さないと作動しない仕組みなど)を積極的に導入します 。
学習する組織文化と教育の仕組み化
失敗を恐れず、継続的に学習できる組織文化を構築することが、レジリエンスを高める上で不可欠です。
- ブラックボックス思考の定着:
失敗した当事者を罰するのではなく、航空機のブラックボックスのように、エラーを客観的なデータに基づいて分析し、「なぜシステムがミスを許容したのか」という視点で原因を究明する文化を確立すべきです。 - ヒヤリハットの積極的活用:
ヒヤリハット報告を「失敗」ではなく、「事故を未然に防いだ成功事例」として共有・評価することで、潜在的なリスクを組織全体で意識し、予防策に繋げます。 - 体系的な教育と情報共有のデジタル化:
OJTに頼るだけでなく、初心者でも理解しやすい図や動画を多用したマニュアルを整備し、誰もが必要な情報にいつでもアクセスできるデジタル基盤を構築することが、知識不足によるエラーを防ぎます。
まとめ:持続可能な安全文化の構築に向けて
芳賀氏が指摘するように、ヒューマンエラー対策は、もはや個人の努力や精神論で解決できる段階を超えています。
目指すべきは、「ミスをしない人間」ではなく、「ミスをしても事故にならない、かつ柔軟に対応できる」強靭なシステムです。
- リスクを生む作業の排除:
集中力の低下や慣れによるミスが起きやすい単純・反復作業を特定し、デジタル技術や自動化によって可能な限りシステム的に排除すること。 - レジリエンスの強化
エラーを罰する文化を廃止し、失敗を組織的な学習の機会として捉える「ブラックボックス思考」を定着させること 。これにより、予測不能な状況においても柔軟に対応・回復できます。
製造業/卸売業に特化した「monolyst」であれば、ヒューマンエラーを可能な限り削減し、
生産性を格段に向上させることが可能です。
----------------------------------------
▼ monolystでできることを確認する
https://corp.mono-lyst.com/product
----------------------------------------
ぜひ、今後のヒューマンエラー対策の一案としてご参考ください。


%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E5%BF%85%E7%84%B6%E6%80%A7%20(8).png?height=200&name=%E7%B4%99%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E9%99%90%E7%95%8C%E3%81%A8%20PIM(%E5%95%86%E5%93%81%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%AE%A1%E7%90%86)%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E5%BF%85%E7%84%B6%E6%80%A7%20(8).png)