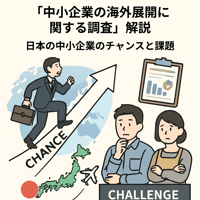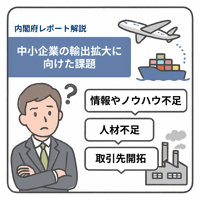「中小企業の国際展開に関する実態調査報告書」レポートに見る日本の中小企業のチャンスと課題
この記事では、東京商工会議所が実施した「中小企業の国際展開に関する実態調査報告書」について、解説します。
はじめに
東京商工会議所は、国内市場の縮小や地政学リスク、為替変動などで不透明感が増す中小企業の現状を踏まえ、海外展開の実態を把握するために調査を実施した。対象は東京23区内の中小企業12,000社で、回答数は1,618件(回答率13.5%)に上った。
調査は2024年7月~8月に行われ、越境ECや生産委託など多様化する国際展開手法の実態を明らかにしている。
海外展開の現状と特徴
国際展開を実施している企業は27.1%。主な手法は「直接輸出」(15.1%)と「間接輸出」(10.1%)で、「越境EC」(2.7%)や「海外企業の買収(M&A)」(0.1%)はまだ少数にとどまる。
業種別では製造業・卸売業が多く、従業員100人以下の小規模企業でも2割が取り組んでいる。国際展開を行う企業は未実施企業より売上が増加したと答える割合が高く、海外展開が業績向上に寄与している実態がうかがえる。
取り組みの動機と課題
海外展開を始めた理由としては「新規市場の開拓」「取引先からの要請」が上位を占める。生産拠点保有企業では「コスト削減」が最多で、11年以上前から取り組む企業が多い。
一方で、進出時の課題は「進め方の知識・ノウハウ不足」が最多で、あらゆる形態に共通する。現在の課題では「ニーズ・市場の把握」や「資金」が挙げられ、特に生産拠点保有では資金面の負担が大きい。
成果と撤退の実情
海外展開を行った企業の6割超が「成果を上げている」と回答。具体的な成果は「新規市場での売上拡大」「生産コスト削減」などが多い。投資額は越境ECや委託生産では50万円以下と小規模だが、生産拠点保有では3,000万~5,000万円規模の投資が必要になる。
一方で、撤退や縮小を経験した企業もあり、その理由は「受注先の確保が困難」「環境変化による販売不振」が中心。撤退前に最も求められた支援は「販路開拓」と「市場調査・競合分析支援」であった。
東京の中小企業5社に見る、海外展開のリアルと成功の鍵
国内市場の縮小や為替変動を背景に、多くの中小企業が海外市場への挑戦を模索している。東京商工会議所の実態調査では、海外展開に成功した中小企業5社の取り組みが紹介されている。それぞれのケースからは、デジタル活用、ブランド戦略、現地適応力など、これからの中小企業に求められる実践知が浮かび上がる。
事例① 倉重電動工具株式会社:SNSと越境ECでDIY愛好家を掴む
大工道具の卸・小売を営む倉重電動工具(足立区)は、国内需要の減少を機に越境ECへ挑戦。Instagramを通じた問い合わせをきっかけに海外販売を開始し、英語対応のECシステム導入で販路を拡大した。
米国人YouTuberによる紹介動画が“バズり”、売上の4割を海外が占めるまでに成長。一方で、関税トラブルや配送コストなど課題も多く、保険加入や配送料調整など独自のリスク対策を構築している。
事例② 横井醸造工業株式会社:ブランド維持のための「販路の整理」
創業87年の酢メーカー横井醸造(江東区)は、赤酢が海外で安売りされブランド毀損の危機に直面。そこで販売ルートを厳格に管理し、現地飲食店への直接指導で品質を徹底。大量販売ではなく小ロット・高付加価値販売に転換した。
海外展開の鍵は「ストーリーで売る」こと。製品の背景を語り、オーナーや料理人を工場に招くなど「体験」を通じた信頼づくりで、赤酢ブランドを世界に確立した。
事例③ 高橋総本店:失敗を糧に「文化を売る」姿勢
浅草・合羽橋の老舗商社・高橋総本店(台東区)は、外国人観光客の増加をきっかけに海外販売を開始。食器や調理道具の輸出で通関トラブルや輸入規制に苦労しつつ、経験を知見に変えて成長した。
近年は日本製かき氷機の海外展開に注力。タイでの展示会を契機に「日本のかき氷」という文化の普及を目指している。「メイド・イン・ジャパン」だけではなく、「物語」や「体験」で価値を伝える重要性を示す事例だ。
事例④ 文京楽器株式会社:「職人技×デジタル」で再挑戦
弦楽器の製造販売を手掛ける文京楽器(文京区)は、かつてコスト削減のため中国に生産拠点を移したが、コロナ禍で国内回帰を決断。日本の職人技にデジタル技術を融合させることで、高品質な「ピグマリウス」ブランドを再構築した。
YouTubeなどを活用した発信で、海外ユーザーとの直接取引(越境EC)も展開。「安さではなく品質で勝つ」日本製ブランドの再評価を体現している。
事例⑤ 株式会社フロンティアワン:問題解決力が海外ビジネスの鍵
海外展示会をきっかけに事業を拡大したフロンティアワン(新宿区)は、現地の物流や支払いトラブル、契約慣行の違いなど、想定外の問題に直面しながらも、ひとつずつ解決策を見出した。
代表者は「海外展開は失敗の連続だが、乗り越える過程に成長がある」と語る。実践的な学びと柔軟な対応力こそが、中小企業のグローバル化を支える原動力となっている。
総括:小さく始めて、地道に続ける
5社に共通するのは、「小さく始め、試行錯誤を恐れない」姿勢だ。越境ECやSNSを活用すれば、限られた資金でも海外市場に挑戦できる。一方で、現地リスクや物流・法規対応などの課題も多い。
重要なのは、単なる輸出ではなく、自社の「強み」「物語」「顧客価値」を明確化し、長期的にブランドを育てること。東京の中小企業が世界で評価される時代は、すでに始まっている。
未実施企業の現状と支援ニーズ
海外展開を行っていない企業のうち、「興味はあるが取り組めない」と答えた企業が約2割存在し、その主因は「人材不足」と「進め方がわからないこと」である。
こうした企業が求める支援として、「販路開拓支援」や「ビジネスパートナーのマッチング」が上位に挙げられた。国や東京都、JETRO、中小機構などによる支援メニューが整備されているが、情報周知と実務支援の橋渡しが課題である。
今後の展望
今後については「現状維持」が67.2%を占める一方で、「新たに取り組む」「拡大する」と答えた企業も27.2%あり、若い経営者ほど積極的な傾向がみられる。海外展開が企業の成長戦略として定着するには、ノウハウ・人材・資金の三位一体の支援が不可欠だ。
成功事例に共通するのは「ストーリーで売る」「文化を伝える」といった自社価値の再定義であり、これが次代の中小企業の国際競争力を左右する鍵となるだろう。
メーカー・卸の海外販路拡大ならmonolyst
monolystは製造業向けAIセールスプラットフォームで、商品マスタと連動した多言語対応したECサイト作成により海外販路拡大に貢献いたします。海外輸出拡大をご検討の方は、ぜひ一度、お問い合わせください。