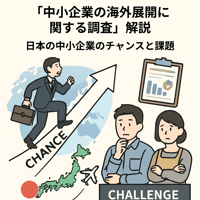この度、monolyst社では、1名〜1000名以上の幅広い従業員規模の企業47社に対してFAX業務実態に関するインタビューを実施しました。そこで見えてきたFAX受注業務の実態と課題を解説します。
商品情報の4Sの重要性とPIMシステム選定の注意点
この記事では、商品情報の4Sの重要性とPIMシステム選定における注意点について、解説します。
1. はじめに:PIM運用に潜む「情報の乱れ」問題
多くの卸・商社やメーカーでは、PIM(Product Information Management)システムの導入後に「列が増える」「同じ品番が複数行存在する」といった課題が生じます。
原因の多くは、同じ意味を持つヘッダー名の表記揺れ(例:直径/刃径/φ)や、微妙に異なる条件で登録された重複データにあります。
こうした“情報の乱れ”は、商品検索性の低下、カタログ生成のミス、EC連携時の不整合といった業務トラブルにつながります。商品情報は企業の基盤資産であり、整備不足のまま運用を続けることは、経営コストと信用リスクを同時に抱えることを意味します。
2. 商品情報における「4S」とは何か
製造現場で用いられる「4S(整理・整頓・清掃・清潔)」は、情報管理にも応用できます。ここでの整理は「不要な情報の排除」、整頓は「必要な情報を探しやすく配置」、清掃は「誤りや欠損を除去」、清潔は「その状態を維持」することを意味します。
商品情報の4Sは、データの品質向上を通じてカタログ生成、EC展開、取引先連携などの精度を高めます。つまり、現場で工具や部品を整然と並べるのと同様に、情報の世界でも秩序を保つことが競争力に直結するのです。
3. 商品データの4S実践:現場で起こりがちな課題と対策
まず「整理(Sort)」では、重複した商品行や使われていない属性列を削除、結合します。
「整頓(Set in order)」では、同義ヘッダーの統一やカテゴリー構造の見直しが求められます。
「清掃(Shine)」では、JANコード桁数の誤りや単位漏れなどを定期的にチェックし、データをクレンジングします。
そして「清潔(Sustain)」では、登録・更新ルールを明文化し、誰がどのタイミングでメンテナンスを行うかを明確にします。
これらを運用ルールとして定着させることが、PIMの効果を最大化する第一歩です。
4. PIMシステム選定における4S視点のチェックポイント
PIM選定では「機能の多さ」よりも「4Sを支える仕組み」が重要です。
データ正規化を容易にする属性マッピングの柔軟性、同義語辞書によるヘッダー統合、品番重複の自動検知などは必須機能です。
また、承認フローを通じて誰が変更したかを追跡できるワークフロー機能も欠かせません。
加えて、他システムとの連携を見据え、ExcelやCSVだけでなくAPI経由でクレンジング・更新できる設計であるかも確認すべきです。
4S視点でのシステム選定は、単なる「データ登録ツール」から「データ品質基盤」への進化をもたらします。
5. 組織としての「データ4S文化」を根づかせるには
PIM導入はゴールではなく、運用文化の始まりです。データメンテナンスを特定の担当者任せにせず、営業・調達・商品企画など部門横断で「情報整備=全員の仕事」という意識を共有することが重要です。
定期的に整備率・欠損率といったKPIをモニタリングし、成果を可視化することで組織文化として定着します。
また、用語統一ガイドラインの策定や教育プログラムの導入により、PIMが持続的に成長する仕組みを作ることができます。
6. まとめ:データ整備こそがPIMの価値を決める
商品情報の4Sは、システムの機能よりも「運用品質」を決定づけます。どれほど高性能なPIMを導入しても、情報の乱れを放置すれば成果は出ません。
逆に、整理・整頓・清掃・清潔が定着した組織では、PIMが確かなデータ資産の基盤となり、営業力や商品提案力の向上につながります。4Sは単なる理論ではなく、日々の小さな整備の積み重ねによって企業競争力を支える思想なのです。
monolystは製造業向けAIセールスプラットフォームで、品番の重複検知やヘッダー列のマージやグループ管理が可能な商品情報管理システムを提供しています。商品情報管理にお悩みの方は、ぜひ一度、お問い合わせください。