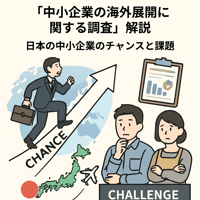経産省「DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて」レポートに見る課題と展望
この記事では、経済産業省「DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて」レポートに見る課題と展望について、解説します。
1. はじめに:DXレポートの警鐘から7年
2018年の「DXレポート」で経産省が示した“2025年の崖”は、既存システムの老朽化・ブラックボックス化により、日本企業がデジタル競争に後れを取る危機を意味していた。7年が経過した今、その崖は目前に迫っている。経産省は2024年から2025年にかけ、企業のDXとレガシー脱却の実態を再調査し、本レポートを公表した。
対象は経営層・情報システム責任者・ITベンダーなど約4,000社であり、現場の声とデータをもとに課題と対処策を体系的に整理している。本稿はその要点をまとめ、企業が今取るべき行動を明らかにするものである。
2. DXとレガシーシステムの現状と課題
調査によると、企業の61%が依然としてレガシーシステムを保有しており、特に大企業ほど比率が高い。システムの老朽化、仕様不明、属人運用といった要素が重なり、維持・改修が困難な状況が常態化している。技術者の高齢化や退職も進み、代替人材の確保が難しい。こうした「過去の遺産」がDX推進のボトルネックとなり、新技術の導入やデータ活用を妨げている。
加えて、経営層がITを「コスト」と捉え、戦略的投資として扱わない文化も改革を阻んでいる。結果として、企業間・国際間のデジタル格差が拡大し、日本の競争力は低下の一途を辿っている。
3. DXの本質:単なるシステム刷新ではない
DXは、単に古いシステムを新しく置き換えることではなく、デジタル技術を軸に企業の業務・文化・組織を変革し、競争上の優位を再構築することを意味する。社会の変化に素早く対応し、顧客や社会のニーズに合わせてビジネスモデルを変化させる「柔軟性」が本質だ。
企業はデータを中心とした意思決定を行い、変化を常態化する「適応力の組織」を築く必要がある。経産省は、レガシー刷新を“目的”ではなく、“変革の手段”と位置づけるよう強調している。単なるIT投資ではなく、企業文化の変革を伴う経営課題であることを忘れてはならない。
4. 産業構造の壁:低位安定のSIモデル
日本のソフトウェア産業は、ユーザー企業がIT開発をベンダーに丸投げし、ベンダーは受託で安定収益を得るという「低位安定構造」に長く依存してきた。結果として、ユーザー側の自律性は低下し、システムは企業ごとに個別仕様が積み重なり、標準化・共通化が進まなかった。
グローバル市場で競争力を発揮するためには、企業が自社ITを“自分ごと”として設計・運用する必要がある。ベンダーもまた、単なる請負型ビジネスから脱却し、価値提供型・共創型のモデルへと進化しなければならない。構造変革が進まなければ、DXは「掛け声倒れ」に終わるだろう。
5. 市場調査から見える実態
調査では、レガシーシステム保有率が6割超にのぼり、特に製造業・物流業など社会インフラ系で深刻だった。経営層がIT課題を経営課題として認識していないケースが多く、中期経営計画でシステム刷新を明記する企業はわずか12%にとどまる。
経営層と情報システム部門の間の情報共有が不十分で、意思決定に必要なデータやコスト情報が共有されていないことが明らかになった。情報システム部門がブラックボックス化したシステムの維持に追われ、戦略的DXを推進できない構造的問題が浮き彫りになっている。
6. モダン化の障壁と人材ギャップ
システムのモダン化を阻む最大の要因は、「現行機能保証」への過剰なこだわりと、業務部門の変化への抵抗だ。業務の見直しを避け、過去のやり方を踏襲する傾向が強い。
さらに、データ移行や相互運用の難しさ、技術的負債の蓄積により、移行プロジェクトは高コスト・長期間化しがちである。IT人材の需給ギャップも深刻で、2025年度には上流人材の充足率が66%にとどまる見通し。
特にITアーキテクトやデータサイエンティストなどの高度人材が不足しており、生産性を補う代替技術(生成AIなど)の活用が急務となっている。
7. 対処の方向性:企業の取るべき行動
経営層はまず、システムを「見える化」することで全体像とリスクを把握し、優先度を付けて内製化と標準化を進める必要がある。内製化は単なるコスト削減ではなく、変化に迅速に対応するための自律的な能力構築だ。
標準化にあたっては、業務プロセスの見直しと現場の理解が不可欠であり、SaaSやクラウド移行を前提にすることが望ましい。大企業だけでなく中堅・中小企業もパッケージ利用を原則とし、スクラッチ開発を減らすべきだと指摘されている。
8. 経営層とベンダー企業の意識改革
DX推進は、経営層の強い覚悟なしには進まない。経営者がシステムを“コスト”ではなく“投資”と捉え、自社のレガシー構造を「自分事」として把握することが出発点だ。
一方、ベンダー企業も従来の請負型から脱却し、コンサルティングや共創支援へと役割を変える必要がある。多重下請け構造を温存したままでは、上流工程の人材育成も進まない。経産省は、ユーザー企業とベンダーが“対等なパートナーシップ”を構築することが、産業構造転換の鍵だと強調している。
9. 地方・中小企業と循環型エコシステム
地方や中小企業は、リソース不足ゆえにモダン化が進みにくいが、業界横断での人材共有・ナレッジ循環によって対応できる。経産省は、テンプレート化・自動化を活用し、レガシー移行の知見を地域で共有する「循環型エコシステム」の形成を提唱している。
ベンダーは開発プロセスを自動化し、ユーザー企業が自律的に活用できる仕組みを提供することで、地域のITリテラシーを底上げすることが期待されている。
10. 政策と今後の展望
政府は、企業が自らDXの成熟度を診断できる「自己診断ツール」や、スキル可視化・キャリア形成を支援する人材育成プラットフォームの整備を進めている。
さらに、企業がモダン化に取り組むためのインセンティブ制度も検討中だ。DXの推進は、一過性のプロジェクトではなく、経営と社会を貫く「継続的変革プロセス」である。経産省は、レガシー脱却を単なるIT課題ではなく、日本経済全体の競争力回復の基盤と位置づけ、企業・政府・社会が一体で取り組む必要性を訴えている。
メーカー・卸のDX推進ならmonolyst
monolystは製造業向けAIセールスプラットフォームで、AIを活用したカタログ解析と商品マスタ自動作成、FAX受注の効率化、Web受発注や通販の推進などにより売上拡大に貢献いたします。DX推進ご担当の方は、ぜひ一度、お問い合わせください。

.png?height=200&name=2025%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%B4%96%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%A8%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E5%AF%BE%E7%AD%96%20(1).png)