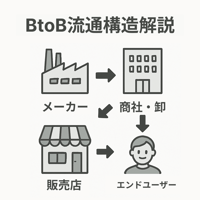卸・商社が通販会社に商品提案する際の価格設定のフローと注意点
この記事では、卸・商社が通販会社に新商品提案する際のプライシング・値付けの方法について、解説します。
はじめに
モノタロウやアスクル、ミスミなどの通販企業に商品提案を行う際、価格設定(プライシング)は最も重要な要素のひとつです。
ここでは、工具卸が通販会社向けに商品提案を行う際の「価格設定の流れ」と「実務上の注意点」を4ステップで整理します。
1. 想定売価の算出
1-1. すでに市場で販売されている場合
まず、自社が提案しようとしている商品がすでに他の通販サイトで販売されているかを調べます。
ベンチマークとして有用なのは以下のようなサイトです。
-
トラスコ オレンジブック.Com
→ 工具卸系の代表的通販。定価・販売価が明示されており、業界標準を把握しやすい。 -
ミスミ VONA
→ 加工部品などで参考価格の算出が容易。 -
アスクル・LOHACO
→ オフィス・現場用品領域での価格水準を知るのに適している。
これらで「市場売価レンジ(定価・実売価)」を確認し、通販会社で想定される販売価格を推定します。
同一カテゴリ内で競合商品がある場合は、対象の通販会社がどの程度の値引き率で販売しているかを観察するのが有効です。
1-2. 通販で販売実績がない場合
もし、どの通販でもまだ販売されていない新規商品であれば、「同一カテゴリ・同用途の比較商品」を調べて価格帯を設定します。
たとえば:
-
同カテゴリ(例:六角レンチ)の他社ブランド価格
-
材質・仕様が近い製品の価格帯
-
PB(プライベートブランド)との価格差
この段階で「市場で受け入れられる売価レンジ」を明確にしておくことが、後の利益計算の基礎となります。
2. 通販会社の利益率を考慮する
通販企業は、販売価格のうち一定割合を利益として確保します。
決算書を確認すると、例えば、モノタロウの売上総利益率はおおむね30%弱です。
したがって、卸として提案する際は、
想定売価 × (1 - 通販利益率) で、通販側の仕入想定価格を逆算するのが基本です。
例:想定売価 ¥1,000 × (1 - 0.30) = ¥700
通販会社の仕入希望価格 ≒ ¥700前後
この「逆算思考」を持っておくことで、現実的な卸値交渉ラインが見えてきます。
3. メーカー指定の卸売価を確認
一部メーカーは、卸売価格や下代を指定している場合があります。
この場合、 通販会社向け提案でも原則その価格体系を守る必要があります。
ただし、
-
メーカーがEC販路に対して柔軟な価格設定を認めているか
-
メーカー希望小売価格(MSRP)と市場売価の乖離がどの程度か
を確認することが重要です。
特にB2B商流とEC商流の価格整合性が取れていないと、他販路とのトラブルの火種になりかねません。
4. 自社の利益率を確保する
最後に、自社としての目標利益率を加味します。
通販経由では、通常のBtoB卸に比べて物流・販促負担が少ないため、
やや低めの利益率でも成立するケースがあります。
ただし、
-
倉庫直送なのか、ドロップシップ型なのか
-
在庫負担をどちらが持つのか
-
返品・不良品の取り扱い条件
など、取引条件によって実質的な原価構造が変わる点に注意が必要です。
最終的には以下のように算出します:
想定売価 × (1 - 通販利益率) × (1 - 自社目標利益率) = 目標仕入価格(メーカー仕入基準)
まとめ:プライシングの基本フロー
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 想定売価算出 | 市場価格調査(トラスコ・ミスミ・アスクル) | 同カテゴリ比較も有効 |
| 2. 通販利益率把握 | 通販会社の粗利率 | 決算書から逆算 |
| 3. メーカー指定価格確認 | 下代指定がある場合は要遵守 | 商流トラブル防止 |
| 4. 自社利益率設定 | 自社原価と販管コストを考慮 | 在庫・返品条件も確認 |
注意点と実務Tips
-
通販会社のPBとの競合チェック:同カテゴリでPBがある場合、価格勝負では分が悪い。差別化要素を明確に。
-
定価からの割引率で整理する:社内管理を容易にするため、「定価→販売価格→仕切価格」を一貫して算出。
-
商流条件を早めに詰める:直取引か代理店経由かで利益構造が大きく変わる。
- 定期的な見直し:為替変動や仕入価格改定を年1回見直す習慣を。
おわりに
通販会社への商品提案は、単に「安く出す」ことではなく、市場理解 × 商流理解 × 自社収益バランスの三拍子が求められます。
この記事のフローを基に、自社の販売データやコスト構造を組み合わせて、より精緻なプライシング設計を行うことが成功の鍵です。
monolyst株式会社は、紙カタログをAI 解析し自動で商品マスタする「monolyst」を提供しています。プライシングに必要な市場データ収集のご支援も行なっております。プライシングや商品登録業務にお悩みの方は、ぜひ一度、お問い合わせください。